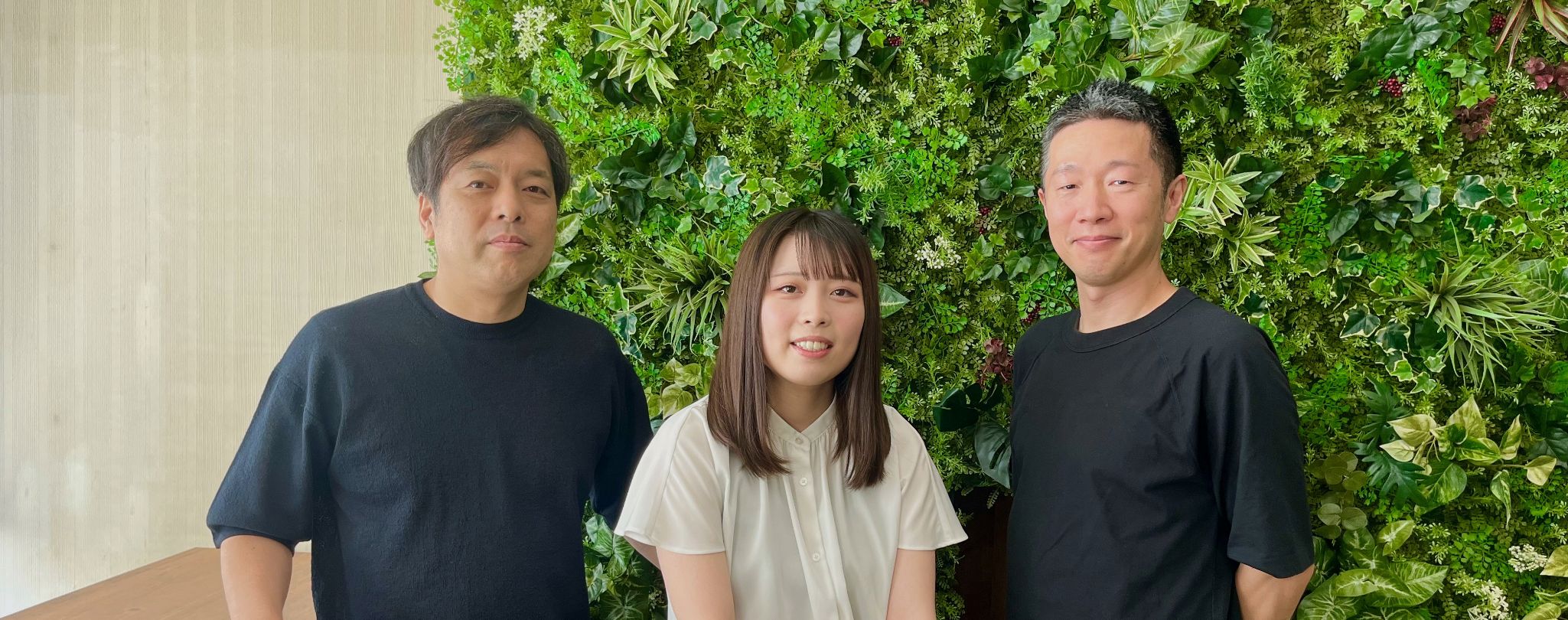

内製化が開く次世代金融サービスの未来。
横浜銀行だからできる価値の創出に向けて
横浜銀行だからできる価値の創出に向けて
デジタル技術を活用して銀行業務の最適化に取り組む横浜銀行。
近年は開発業務の内製化にも力を入れ、今年2月にはキャリア人財を中心にアジャイル開発チームが新設されました。
同チームを立ち上げたITソリューション部の河原 孝尚、メンバーの嵯峨野 憲作、平子 優果が、当行で開発を行う醍醐味、めざす未来を語ります。

- デジタル・IT
- 15年目~
- 文系
- キャリア
ITソリューション部 企画グループ
エグゼクティブプロフェッショナル
2007年キャリア入行
河原 孝尚

- デジタル・IT
- 1~6年目
- 文系
- キャリア
ITソリューション部 企画グループ
2023年キャリア入行
平子 優果

- デジタル・IT
- 1~6年目
- 理系
- キャリア
ITソリューション部 企画グループ
リーダー
2023年キャリア入行
嵯峨野 憲作
※紹介行員のインタビュー内容・所属等は取材当時のものになります
※組織変更に伴い「ICT推進部」の部名は「ITソリューション部」に変更(2025年4月)
地銀大手が推進するアジャイル開発の現場。
新時代の銀行システムを実現するために
新時代の銀行システムを実現するために
- 横浜銀行の幅広い金融サービスを支える300以上もの業務システム。その設計・開発・運用を担っているのがITソリューション部です。

- 河原:「お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループ」をめざし、ITソリューション部では「お客さまの期待を超えるサービスの提供」をITビジョンとして掲げています。その実現に向けて、急速に進むデジタル化と刻々と変化するユーザーニーズに俊敏に対応することが、アジャイル開発チームのミッションです。
- 2024年2月に新設されたアジャイル開発チーム。メンバー5名のうち、3名はキャリア入行者で構成されています。

- 嵯峨野:当チームは発足して間もない組織であり、現在は試行錯誤しながら体制を整えている段階です。私以外のメンバーが同世代ということもあり、和やかな雰囲気の中にも新たな挑戦に取り組む全員の熱意が感じられる、非常に活気に満ちたチームとなっています。
- ITソリューション部 企画グループのエグゼクティブプロフェッショナルとして、アジャイル開発チームを統括する河原。信用金庫のシステム部門、コンサルタントファーム、第二地方銀行を経て2008年に入行しました。

- 河原:基幹系システムの導入に合わせて、システム監査要員として入行しました。その後、ITソリューション部に異動し、預金、インターネットバンキング、ATMやスマホ決済業務などのIT分野を担当し、2022年に現在の役職に就任しています。

- 一方、アジャイル開発チームのメンバーとして活躍する嵯峨野と平子。嵯峨野は2023年1月に、平子は2023年11月にそれぞれキャリア入行しています。

- 嵯峨野:前職は、製造業でIoTサービスの開発に携わっていました。当行がシステムの内製化を始めることを知り、組織づくりから参画できる点に強く惹かれたのが入行の理由です。面接で河原さんが内製化のビジョンを楽しそうに熱く語っていたのが印象的で、その一翼を担いたいと考えました。

- 平子:私は入行前、システムの運用保守を担当していました。ITと金融の知見を活かせるキャリアを模索する中で出会ったのが当行です。前職では業務の幅に限界を感じていたので、システムの内製化という新たな挑戦に大きな魅力を感じ、入行を決めました。
- 銀行での開発業務は初めての2人。入行後は良い意味でのギャップがあったと言います。

- 平子:地方銀行に対して、保守的で古い慣習が残っているイメージがあったのですが、実際には新しいことに挑戦しようとする姿勢が強く感じられます。中でも私たちが所属するアジャイル開発チームは、とても先進的でチャレンジングな業務を担っている組織の1つです。

- 嵯峨野:私も銀行には堅いイメージを持っていたので、誠実でありながら、親しみやすい人が多いことに驚きました。現在、部内では執務室のフリーアドレス導入やコミュニケーションイベントなど、チームを超えた交流の取り組みが進められており、普段接点のない仲間と意見を交わす機会が増え、組織の多様な側面を知ることができています。
- これまで開発業務は外部委託されており、横浜銀行で初のアプリケーションエンジニアとして採用された嵯峨野。未経験の金融業務を覚えるにあたり、周囲の手厚いサポートに支えられてきました。

- 嵯峨野:調べても理解できない専門用語があった時など、気軽に周囲に質問できる雰囲気があり大変助かっています。対面はもちろんオンラインのコミュニケーションツールを使った相談もでき、日々の業務の中で柔軟にサポートを受けられる環境があります。

- 平子:私は嵯峨野さんに続き、当行で2人目に採用されたエンジニアです。今後、キャリア入行者が増えていくことを想定し、後に続くエンジニアがよりスキルアップができるよう、研修制度の充実化も進めてもらえています。

開発ノウハウの蓄積に向けて内製化を推進。
経験豊富でビジョンに共感できる人財を採用
経験豊富でビジョンに共感できる人財を採用
- 入行17年目を迎える河原。高度な専門性を有するITスペシャリストの立場でアジャイル開発チームの活動を支えています。

- 河原:エグゼクティブプロフェッショナルとして、銀行システムとその周辺技術に関する専門知識を共有し、メンバーを後方支援することが私の主要な役割です。
当行では、卓越した専門性を有する人財を「プロ人財」として認定しており、エグゼクティブプロフェッショナルはその1つ。現在は直属の部下を持たずに、アジャイル開発チームの統括を含む複数のシステム企画業務に専念しています。
- チームの中核を担う嵯峨野と平子。現在は同じ開発プロジェクトに従事しています。

- 嵯峨野:私はスクラムマスターとしてチームを牽引しています。スクラムとはアジャイル開発手法の1つで、スクラムマスターは調整役を担います。前職でもスクラムマスターの経験はありましたが、今回は当行で初の内製化プロジェクトです。そのため現在は、予算確保に向けた社内手続きの調整や研修の整備など、組織づくりにも携わっています。

- 平子:私はスクラム開発の経験が浅いため、嵯峨野さんに勧めてもらった外部研修に参加し、スキルアップにも励みながら開発者としてプロジェクトに参画しています。今後の開発で活用する外部のライブラリやフレームワークの検証に向けて、スパイクソリューションを適用した模擬アプリケーションの作成に取り組んでいるところです。
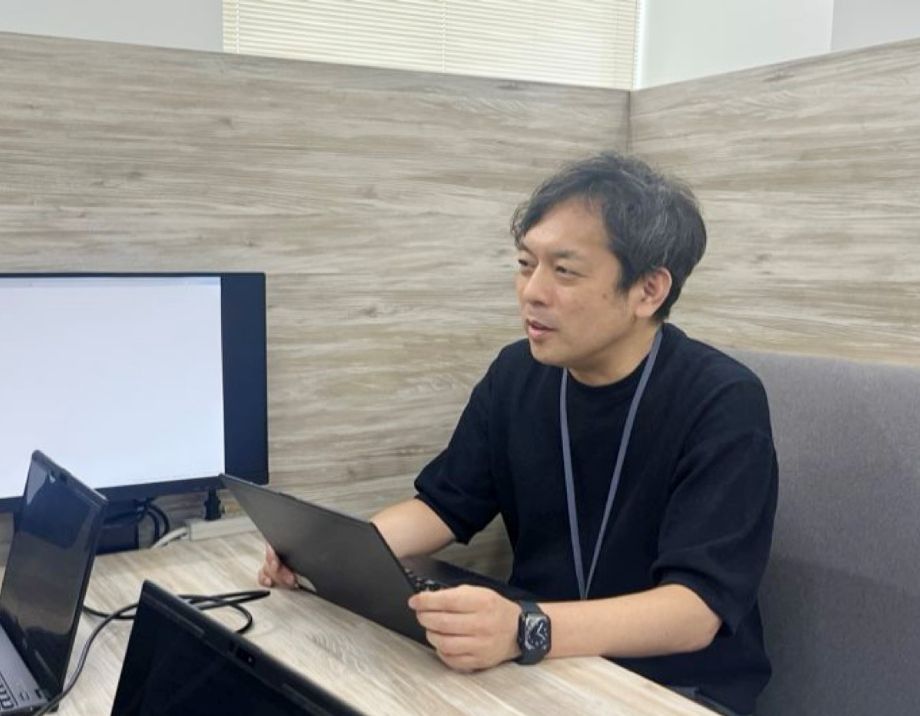
- 横浜銀行で内製化プロジェクトがスタートしたのは2020年のこと。そこから試行錯誤を経て、アジャイル開発チームが立ち上げられました。

- 河原:内製化の第一歩として取り組んだのが、次世代型営業店端末「AGENT(エージェント)」の追加開発です。社内にナレッジを蓄積する仕組みの構築をめざし、行員2名と協力会社5名でチームを立ち上げました。しかし協力会社はエンジニアの流動が激しく、チーム運営での苦戦が続きました。
この経験から、協力会社への依存度が高い開発に限界を感じ、約1年前に行員主体のエンジニアリングチームの立ち上げを企画しました。これが現在のアジャイル開発チームの起源となっています。
- アジャイル開発チームの新設にあたり河原が直面した課題が、「共に挑戦してくれるエンジニア」の採用でした。

- 河原:当行にとって自社開発は未踏の領域です。前例がない取り組みである以上、まず内製化という新しいプロジェクトの意義を社内に理解してもらう必要がありました。
また、人財の確保も予想以上に苦労した点です。外部ベンダーを活用する従来のモデルであれば、必要に応じて柔軟に人員を調達できますが、内製の場合はそうはいきません。
私たちが求めていたのは、高度なエンジニアリングスキルと豊富な経験を有し、なおかつ新しい組織づくりに対して強い意欲と情熱を持った人財です。
ビジョンに共感し、共に挑戦してくれる仲間を見つけることが最重要だと考えていました。そしてその人財像に合致した第1号エンジニアとして嵯峨野が入行し、そこに平子が加わり、ようやく描いていた内製化チームが動き出したと感じています。
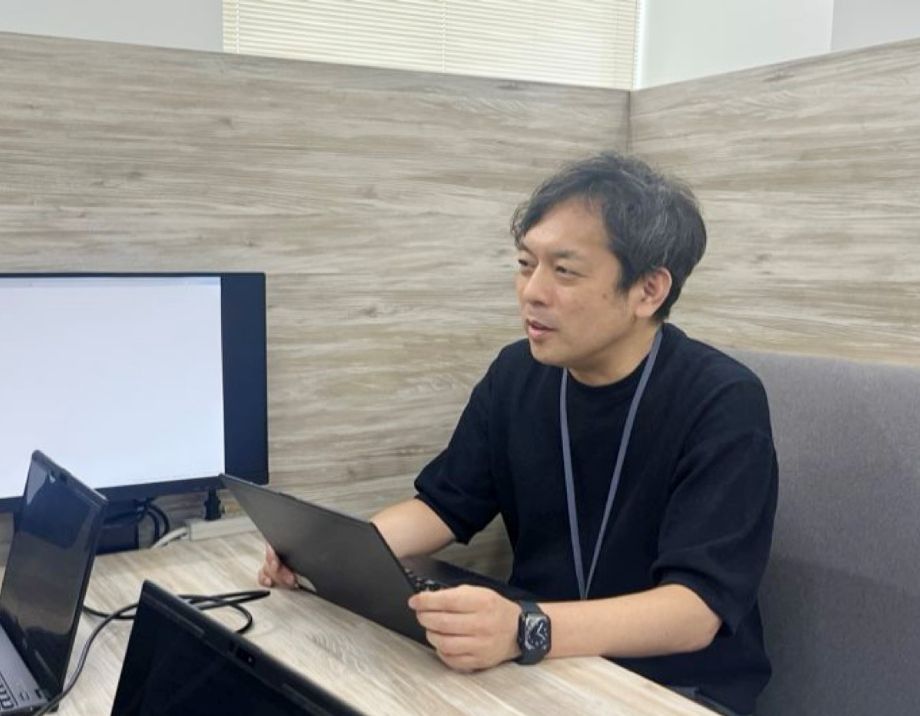
裁量の大きさが育むイノベーション。
挑戦に開かれた環境が成長のきっかけに
挑戦に開かれた環境が成長のきっかけに
- 即戦力として活躍してきた嵯峨野と平子。それぞれ入行して間もない時期に、確かな成長を実感する出来事がありました。

- 嵯峨野:「AGENT」の開発から派生した、PoCのプロジェクトが印象に残っています。依頼元である事務サービス部と協力しながら、ベンダーの力を借りて2カ月という短期間で機能を開発し、営業店で実証実験を行いました。
フィードバックを受けて改善を重ねる中でアジャイル手法を実践でき、ユーザー部門からも高い評価を得ることができました。当時、銀行側の開発者は私ひとりでしたが、「良い製品を開発したい」というユーザー部門の想いにみんなが共感し、チームが一体となって活発に議論できたことが成功の要因だと思っています。

- 平子:私にとって印象深いのは、お客さまの手続きをデジタル化するサービスを、外部のソリューションを活用して開発した経験です。それまでバックエンド中心でしたが、初めて本格的にフロントエンドの開発に挑戦する機会を得ました。
質問しやすい職場環境があり、また行内の生成AIチャットサービスや外部研修などのサポート体制が充実していたため、経験が浅い領域でも不安なく取り組めました。新たな分野で自らコードを書いて修正する経験を積むことができ、大きな自信につながっています。
- アジャイル開発チームを立ち上げから見守ってきた河原。エンジニアが成長できる環境の魅力をこう語ります。

- 河原:現在進行中の個人のお客さま向けサービスの開発プロジェクトでは、嵯峨野と平子を含む4名に加え、協力会社から3名、さらに部内の別グループからインフラエンジニア1名を招聘し、計8名の開発チームを編成しています。
今回のプロジェクトの特徴は、開発環境やツールの選定を含め、一からすべてをチームメンバーに委ねている点です。この取り組みを通じて、メンバーが多様な経験を積み、さらに強いチームになると信じています。
今後もチームに裁量を委ねる開発スタイルを継続し、システムを一度構築して終わりにせず、常に最新の技術に挑戦し続ける組織づくりを推進していきたいと考えています。

- 一方、チームメンバーの2人も河原の意見に共感しながら、さらに次のように続けます。

- 嵯峨野:一からシステムを構築しているからこそ、自分の意見や好み、挑戦したい技術について自由に発言できるのだと思います。興味のある分野に携わり、エンジニアとして成長できる機会があることがアジャイル開発チームの魅力です。

- 平子:自分がやりたいことを実現する機会が豊富に与えられていて、学びたいことを自由に探求できる環境にとても満足しています。この環境を活かし、今後私たちのチームに加わってくださる方を指導できるようになるくらい、知識を高めていきたいと考えています。

企画からリリースまで一貫体制。
豊富なアセットと知見で地銀ならではの開発を
豊富なアセットと知見で地銀ならではの開発を
- DXを推進する上でも重要となる内製化。横浜銀行でこの取り組みに携わる醍醐味について、それぞれ次のように語ります。

- 河原:当行には創業100年以上の歴史の中で培った実績があり、IT部門だけでなく本部の各部門において銀行業務に精通したメンバーが多数在籍しています。新しいサービスの提供にチャレンジできるのは、こうした豊富なアセットとリソースがあるからこそです。革新的なサービスを生み出すための土壌が整っていると感じています。

- 嵯峨野:銀行内の開発者として、企画段階から携われることが醍醐味です。プロダクトの構想から開発、リリースまで一気通貫で担当できるのは当行ならでは。自分たちが開発した製品をお客さまに使っていただけることは、エンジニア冥利に尽きます。

- 平子:前職ではすでに決定された要件にもとづいて開発するだけでしたが、当行ではキャリアや年次に関係なく要件定義やプロダクトの方向性の決定などにも携わることが可能です。エンジニアとして他の金融機関にはないおもしろさがあります。
- 内製化の推進に向けて挑戦は始まったばかり。3人が描いているビジョンがあります。

- 河原:現在のプロダクト開発をパイロットプロジェクトと位置づけており、これを通じて今後の内製化拡大に向けた基盤固めをすることが直近の目標です。チームの適切な運営と強化を可能にする土壌とカルチャーの醸成に注力したいと考えています。
そして成果を出すことで開発体制をさらに拡大し、他の地方銀行にも展開できるようなサービスを開発することが私の最終的なビジョンです。

- 嵯峨野:アジャイル開発の真価を発揮するべく、ユーザー部門の潜在的なニーズを汲み取ってそれを共に実現し、期待を超える成果を生み出すチームをつくることが私の目標です。
チームにはキャリア入行者が多いため、銀行の業務知識や既存システムに対する理解をさらに深める必要があります。自主的に窓口業務に関する研修に参加したり、行内システムの有識者から指導を受けたりしながら、より優れたプロダクトを生み出せる環境づくりをめざしていきたいです。

- 平子:開発者として、2人のように豊富な専門知識と高度なスキルを持つエンジニアになることが第一の目標です。一般的な開発知識はもちろん、クラウドを含む最新技術の習得にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。

- 内製化の未来を担うアジャイル開発チーム。その体制強化に必要なのが、組織と共に挑戦できる人財です。これから迎える新たな仲間に向けて、3人は次のように呼びかけます。

- 嵯峨野:個人だけでなく、チーム全体の成長を重視できる方を歓迎します。ものづくりへの情熱や新たな挑戦への意欲を持ち、ユーザーの喜びを直接感じられる。そうした方の参加をお待ちしています。

- 平子:管理職のメンバーも積極的に資格取得に励むなど、自己研鑽の精神が根づいていることが当行の特徴です。成長に対して意欲的な方ほど当行の文化になじみ、活躍できると思います。

- 河原:私たちがめざしているのは、飛び抜けた技術を持つ人財に頼るチームではありません。嵯峨野が言うように、相互に助け合いながら、成長できるチームが理想です。仲間と共に継続的なスキルアップに取り組める方と出会えることを楽しみにしています。
